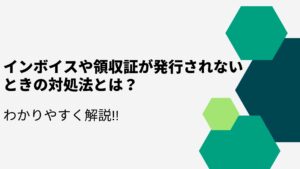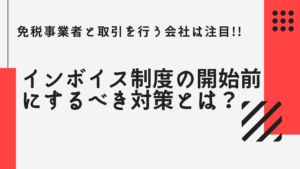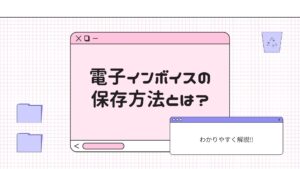インボイス制度が開始すると問題になるのは、免税事業者との取引になります。
開始してから数年間は経過措置が設けられているとはいえ、今後、継続的に免税事業者と取引をするにあたって何か対策をしなければなりません。
そこで、今回はインボイス制度によって課税事業者が損しないためにはというテーマで免税事業者との取引においての注意点について解説します。
買い手側が注意すべき点、免税事業者と取引する上での注意するポイントをまとめています。
適格請求書発行事業者に申請が完了したけど、免税事業者との取引がある会社や実務担当者に必見の記事ですので、ぜひ、最後までご覧ください。
この記事をぜひ読んでほしい方
・免税事業者との取引がある実務担当者
・課税事業者だけど、インボイス制度の開始後、損しない手法を知りたい実務担当者
買い手側がすべきこと

まず、課税売上高が5,000万円以下の事業者であれば簡易課税制度を利用した方がよいです。
簡易課税制度を利用するメリットは、課税仕入を考えずに概算によって仕入税額控除をすることができます。
つまり、仕入税額控除にインボイスそのものが不要になります。
言い換えると、免税事業者から今まで通りの条件で仕入をしたとしても消費税の納税する金額は変わらないということが実現できるのです。
そうすることで、免税事業者に値下げの要求をする必要もなくなります。
ただし、業種によっては簡易課税制度を利用する方が納税する負担が課税事業者になるよりも大きくなる場合があるので、事前に確認しましょうね。
免税取引事業者と取引する上での注意点

免税事業者の中で、適格請求書発行事業者を申請しない事業者も中にはいるでしょう。
そういった事業者と取引をする場合、買い手側が仕入税額控除を受けることができません。
免税事業者と取引しなければならない場合は、売り手に対して消費税分の値下げ交渉をしてみましょう。
消費税分以上の値下げ交渉は独占禁止法の問題に関わるかもしれませんが、益税の部分だけは売り手に負担してもらえるように交渉してみましょう。
それでも、免税事業者が消費税分の値下げ交渉の負担に応じない場合は取引先の変更を検討してもいいかもしれません。
取引先の変更が難しい場合は、インボイス制度の経過措置の間は取引先の変更を保留して様子を見るのもいいでしょう。
ちなみに、インボイス制度の開始から3年間は仕入消費税額相当額の80%、その後の3年間は仕入税額相当額の50%は仕入税額控除ができるので、経過措置を利用しましょう。
まとめ
今回は、インボイス制度によって課税事業者が損しないために免税事業者との取引においての注意点について解説しました。
インボイス制度が開始してから免税事業者と継続的に取引することは買い手側にとって不利になってしまいます。
買い手が大きな負担を避けるためにも、免税事業者が適格請求書発行事業者になってもらうか、消費税分の負担をしてもらうか、免税事業者に対して積極的に交渉してみましょう。